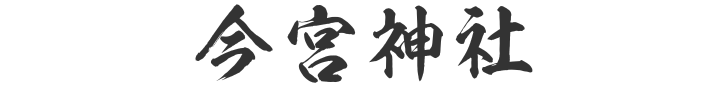今宮をより深く知る
古典文献に見る今宮神社
『百錬抄』
公家の日記や記録を抜粋・編集した歴史書。
鎌倉時代後期(13世紀末)に成立したとされるが、著者・編者は不詳。
もともとは「百練抄」と書かれていた可能性もあり、江戸時代以降に「百錬抄」という表記が一般化。
平安時代(長保年間)に疫病退散を願って創建
永承5年(1052年)の疫病流行で八坂神社の神を勧請
『日本紀略』
平安時代に編纂された歴史書であり、『六国史』の抄本です。
大同以後、天皇歴の記述を含み、神代から長元9年(1036年)までの歴史を記録しています。
編者は不詳であり、原文は漢文体で全34巻からなります。
花園社 → 疫社 → 今宮大明神 → 今宮神社
『小右記』
平安時代の公卿 藤原実資(ふじわらのさねすけ) の日記。
「小右記」とは、小野宮右大臣(藤原実資)の記録であることに由来する。
全61巻が現存し、すべて漢文で書かれている。また、別名として『野府記(やふき)』とも呼ばれる。
厄除け・病気平癒の神社としての信仰
『続古事談』
鎌倉初期の説話集。著者不詳。成立は鎌倉7年(1219年)とされる。
全5巻で、現存本は185話を収録。
構成は、天皇・臣下・公卿・神仏・僧侶に関する説話が収められている。
『平心園記』
江戸時代や明治初期の地誌・随筆・紀行文。
平賀喜次という名前はあまり一般的ではありませんが、地方記録などに見られることがあります。
厄除け・疫病退散・病気平癒・縁結び・家内安全・商売繁盛
「疫病流行と神社信仰」の特集
文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章
今宮をより深く知る
古典文献に見る今宮神社
『百錬抄』
公家の日記や記録を抜粋・編集した歴史書。
鎌倉時代後期(13世紀末)に成立したとされるが、著者・編者は不詳。
もともとは「百練抄」と書かれていた可能性もあり、江戸時代以降に「百錬抄」という表記が一般化。
平安時代(長保年間)に疫病退散を願って創建。永承5年(1052年)の疫病流行で八坂神社の神を勧請
『日本紀略』
平安時代に編纂された歴史書であり、『六国史』の抄本です。
大同以後、天皇歴の記述を含み、神代から長元9年(1036年)までの歴史を記録しています。
編者は不詳であり、原文は漢文体で全34巻からなります。
花園社 → 疫社 → 今宮大明神 → 今宮神社
『小右記』
平安時代の公卿 藤原実資(ふじわらのさねすけ) の日記。「小右記」とは、小野宮右大臣(藤原実資)の記録であることに由来する。
全61巻が現存し、すべて漢文で書かれている。また、別名として『野府記(やふき)』とも呼ばれる。
厄除け・病気平癒の神社としての信仰
『続古事談』
鎌倉初期の説話集。著者不詳。成立は鎌倉7年(1219年)とされる。
全5巻で、現存本は185話を収録。構成は、天皇・臣下・公卿・神仏・僧侶に関する説話が収められている。
『平心園記』
江戸時代や明治初期の地誌・随筆・紀行文。
平賀喜次という名前はあまり一般的ではありませんが、地方記録などに見られることがあります。
厄除け・疫病退散・病気平癒・縁結び・家内安全・商売繁盛
「疫病流行と神社信仰」の特集
文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章文章
御朱印やお守りなどの詳細については、こちらからご確認ください。
ご参拝やご祈願について、よくいただくご質問にお答えしております。
ご参拝・ご祈願に関するご相談やご質問はこちらから承っております。